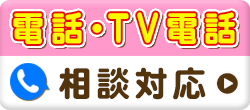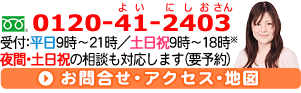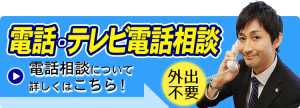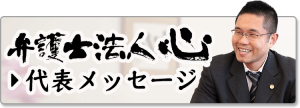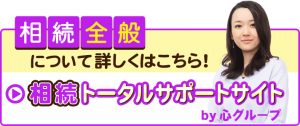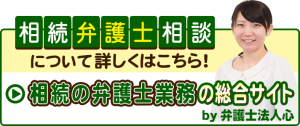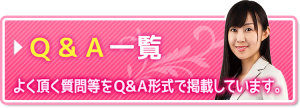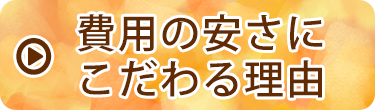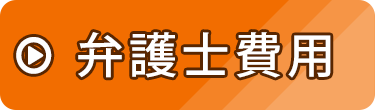相続放棄と管理義務
1 民法改正により管理義務を負う範囲が明確になった
相続放棄をした場合であっても、従来の民法では相続財産の管理を始めることができる相続人が現れるまで、自己の財産と同様の注意をもって、その財産の管理を継続する義務がありました。
しかし、令和5年に施行された改正民法では、この義務が「保存」義務に変更され、保存義務を負う対象も放棄時に「現に占有している」財産のみとなりました。
そのため、現在の民法では相続放棄した人が相続財産を占有していないのであれば、保存義務を負わないことになります。
これまでは地方の不動産などが相続財産としてある場合に、相続放棄しても管理義務が残ることから、相続放棄によっても抜本的な解決ができないことがありましたが、現在の民法ではそうした問題がかなり減少しました。
2 現に占有しているかどうかの判断
このように、現在の民法では相続放棄時にその対象物を現に占有しているかどうかが大事になってきます。
わかりやすい例で言えば、父所有の自宅に父子が同居していた場合がこれにあたります。
父が亡くなった場合、子は相続放棄したとしてもこの自宅に住んでいる以上、現に占有しているということになりますので、相続放棄後も保存義務が発生します。
3 保存義務を怠った場合
例えば、空き家の保存義務を負っている人がその義務を怠り、空き家の価値が減少してしまうと、債権者が本来回収できたはずの金員が減ってしまい、その減額分の損害賠償を求められるということがありえます。
また、古い空き家を修繕せずに放置したことで倒壊してしまい、隣の家に損害を与えてしまったり、通行人にけがを負わせてしまったりという場合も同様です。
4 保存義務を負う場合の対応
相続放棄後の保存義務を負う人が保存義務から免れるためには、相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。
申立てにあたっては数十万円~100万円程度の予納金が必要となるため、将来的に相続放棄を予定している場合で、かつ保存義務を負うことが見込まれるのであれば、相続財産清算人の申立てに必要な資金についてもあらかじめ準備しておくのが望ましいでしょう。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒271-0092千葉県松戸市
松戸1281‐29
京阪松戸ビル3F
0120-41-2403